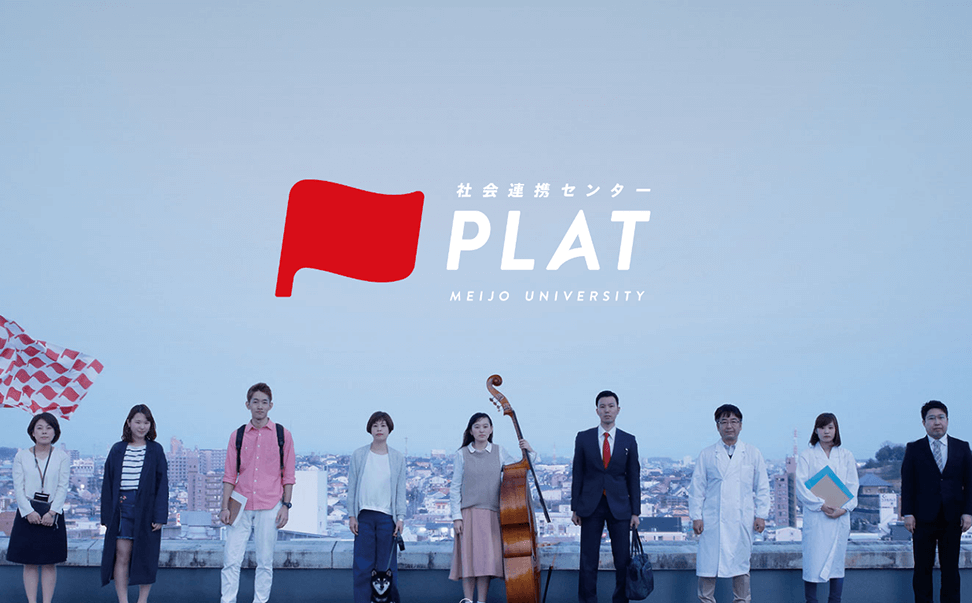トップページ/ニュース 2026年4月、新設「化学?物質学科」体験実験講習会を開催
東海4県の高校1~3年生23人が参加 化学と物理学の実験に取り組む
 化学の実験を体験する高校生ら
化学の実験を体験する高校生ら
2026年4月に本学理工学部に新たに設置される「化学?物質学科(応用化学専攻?材料機能工学専攻)」への関心を高めることを目的とした体験実験講習会が10月25日、天白キャンパスの研究実験棟Ⅱ~Ⅳで開催されました。愛知、岐阜、三重、静岡県から高校1~3年生23人が参加し、教員と大学院生?学生の指導のもと、化学実験と物理学実験に取り組みました。
新学科では「化学と物理学の両方を理解できる人を育てたい」と才田准教授
-
 新学科について説明する才田准教授
新学科について説明する才田准教授
-
 実験の内容を説明する永田教授
実験の内容を説明する永田教授
資源やエネルギーを無駄なく活用し、循環させる「新たな物質?材料の創製」が求められる中、本学理工学部ではこの領域をさらに強化すべく、現在の「応用化学科」と「材料機能工学科」を統合し、「化学?物質学科」を開設します。化学?物質学科では、最先端研究を教育に取り入れ、化学と物理学を横断的に理解し活躍できる研究者?技術者を育成することを目指しています。
講習会ではまず、才田隆広准教授が学科設立の目的や教育体制、特徴的な学びについて紹介し、「大发体育官网_澳门游戏网站にしかない学科として、化学と物理学の両方を理解できる人を育てたい」と語りました。その後、参加者は2グループに分かれ、化学実験「日焼け止めの成分を合成しよう」と、物理学実験「LEDと太陽電池の不思議な関係:光と電子はどうつながっている?」の2テーマの実験に挑戦しました。
化学実験は永田央教授らの指導のもと、水酸化ナトリウム水溶液中でアルデヒドにケトンを加えることで生じる反応や生成物を観察しました。試験管の振とうや湯浴による加熱など、化学実験の基礎操作を体験しました。また、NMR(核磁気共鳴)分光計による分析手法とデータの読み解き方について説明を受け、先端的な研究設備にも触れました。
「先生や学生さんが丁寧に教えてくれたので成功できた」と参加者
物理学実験では岩谷素顕教授および大学院生?学生のサポートのもと、LEDが発光するのに必要な電圧や、LEDに光を照射した際に発生する電圧を測定し、光と電子の関係を学びました。結果を確認しながら質問に答えるなど、積極的なコミュニケーションが交わされていました。実験後には、レーザー加工機でボールペンに名前を刻印するデモも行われました。
参加した生徒からは「難しい内容もあったけれど、実験を通して考えることが楽しかった」「先生や学生さんが丁寧に教えてくれたので成功できた」などの声が寄せられました。また、「もっと応用的な内容も体験してみたい」「実験だけでなく、議論する時間もあると良い」といった前向きな要望も聞かれました。
今回の講習会を通じて、高校生たちは化学と物理学を融合した学びの魅力を体験しました。本学理工学部は、今後もこうした取り組みを継続し、未来の科学技術の発展を担う人材育成に力を注いでいきます。
-
 化学の実験
化学の実験
-
 化学の実験の様子
化学の実験の様子
-
 物理学の実験について説明する岩谷教授
物理学の実験について説明する岩谷教授
-
 院生や学生が実験を指導?サポート
院生や学生が実験を指導?サポート
-
 LEDが光る時の電圧を調べる
LEDが光る時の電圧を調べる
-
 LEDに光を照射
LEDに光を照射
-
 NMR分光計の説明
NMR分光計の説明
-
 レーザー加工機を見学
レーザー加工機を見学